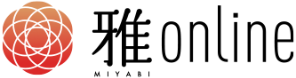『匠探訪シリーズ5:村山刺繍店』伝統の伝承者として挑戦を続けたい
有限会社村山刺繍店 村山 裕俊氏

幅を広げて道を切り開く
平面にふっくらと渡る絹糸。布に彩を与え、豊かな表情を吹き込むのが刺繡だ。「ないと寂しい感じです」という村山氏は4代目。刺繡からスタートした家業だが、染め、悉皆も手掛けてきた。そして、いま。刺繡に原点回帰。工房で一針一針、布目に挿していく気の遠くなる作業で布に命を吹き込んでいる。
着物に華やぎを
艶やかな糸が布の表と裏を渡り、模様を描くと華やかさが増す。花びら一枚、葉脈一筋に糸があるだけで、染めだけの着物とは異なる風情が生まれる。これが刺繡の魅力だ。村山氏は「女性のお化粧のようなものです」と表現する。すっぴんの女性も魅力的だが、お化粧をして正装した女性には品も趣も艶めきもある。刺繡はこの化粧にあたるものであり、施すことで着物の表情に深みが増すのだ。
刺繡がないと、なんとなく寂しい・・・・と思う人は多いようで、「加賀友禅に刺繡をしたことがある」(村山氏)ほどだ。
通常、加賀友禅には刺繡は入れない。写実性を重んじ、花鳥、草などを忠実に描くのが加賀友禅の特徴。葉を虫が食べたような跡を表す虫食いといわれる表現やぼかしを使い、京友禅と異なる雰囲気だ。加賀五彩(藍、臙脂、草、黄土、古代紫)で、色調もどちらかといえば、落ち着いたもの。これは加賀藩、前田家100万石の城下町で発展した背景があるからだろう。
だが、この落ち着きやしっとりした情趣はともすれば寂しい雰囲気にもなりかねない。そこで、刺繡をお願いしたいということになったである。
華やかさやあでやかさ、ときにしっとりとした情趣を加えるのであるから、面積は小さくても、刺繡の力は大きい。
ただし、刺繡は入れればいいというものではない。着物全体にとりどりの色や立体感があると目が休まらず、ガチャガチャしたものになってしまう。繡のよさを引き立てるのは間=余白である。染めの色と白の対比。そこに、刺繡のひとさじの色味。調和とバランスが着物の完成度を高める。
では、どの余白を活かし、どこに、どのような刺繡をどのような色で入れるのか。この勘所が長年にわたる経験と磨き抜かれたセンスだ。現代は色味を絞りつつ、シンプルな方向へ向いているというが、こうしたトレンドを読む感性も求められる。

他方、御所解き模様など、古典柄は基本に忠実でないと違和感が出る。かといって、正倉院柄模様では異国情緒をいかしながらも和風にアレンジしなければ、とがったものになってしまう。
何をいかし、どこをアレンジし、どこに刺繡をするのか。同様の色味のなかからどの色を選び、糸の本数をどうするのか。最終工程を受け持つ同社は細部にまで神経をいきわたらせ、布に新たな命を吹き入れ、着物という完成品をつくりあげる。
時間がかかる人材育成 それでも国産にこだわりたい
表面に凹凸を与え、着物を華やかに彩り、豊かな表現を実現する刺繡。工房では静謐な空間で緻密な作業が続けられる。金糸が布を往復するときのキュキュッという音が時折聞こえる。
緊張感があり、細かい仕事はやはり疲れも出る。長時間、続けると効率が悪くなるため、3時間おきに休憩を挟み、1日中、布に向き合う。
1日中向かい合うのであるから、すぐに上達するのではないかと思うが、実は職人として一通りできるようになるのに5年、数多くの技法をマスターして使いこなせるようになるには10年の歳月が必要だという。

入社して、最初の作業は糸を撚ること。この段階で布に触ることはない。
この糸を撚る作業が奥深い。通常、刺繡に使われる糸は釜糸という撚りがかかっていない1本の糸である。これを柄のデザインやイメージに合致するように撚り合わせていくのだ。複数本を合わせてねじりを加えることで、絹糸の光沢が増すと同時に強度も出る。
より合わせる糸の数で太さを調整するが、撚るときに複数の色を一緒に撚ることもある。こうすることで同じ色を数本撚り合わせるものとは異なる微妙な色が表現できる。また、撚りの強弱によって絹糸の光り方が異なるという複雑さ。さらに糸を撚らずにそのまま使うこともある。糸を撚る、刺繡の第一歩だが、糸の太さも色も自由にできる面白さと難しさがあるのだ。
次のステップで技法を学ぶが、これが根気のいる仕事。
一例をあげてみよう。模様の輪郭を際立たせるために行う駒取という技法がある。金糸や銀糸を下絵通りに置き、別糸で目立たないように留めていくもの。技法は鎌倉時代以降のものだが、現代でも輪郭や強調したい部分によく使われる。留める糸は目立たないように細い糸を使うが、留める間隔は一定である。
しかし、人間が等間隔、それも㎜以下の単位で同じ間隔に針を往復させるのは至難の業。体調、気候(湿度によって糸のテンションが変わり、布と針の摩擦が変わるため、針の滑りも違う)、気分に関係なく同じリズムで針を動かす・・・・もう、無心の境地である。これが熟練というものだろう。

さらに例を上げてみよう。相良縫いという技法だ。縫物をするときに糸の最初に作る玉結び。この玉結びの集合体といえばいいだろうか。立体感があり、細かい表現が可能だ。ポコポコとした球が並んで模様となる様子は上品で大人かわいい。
だが、小さなものの集合体で一つの“絵”を表現する労苦をイメージしてほしい。何万回、結べばいいのだろうか。しかも、一つひとつの玉結びが手順にのっとっていても、大きさがバラバラでは調和がとれない。同じ大きさで結び、次に結び。さらに結び。色を変えて結び。さらに結び・・・・。 気の遠くなるような作業だ。
同社の職人はすべて女性。全員が様々な職種ができるよう多能工だ。村山氏は女性の柔軟性としなやかさに期待する。「臨機応変に対応でき、細かい仕事ができる。さらに根が続く」。一人が複数の技法を習得し、複数の工程を担当できる多能工化も女性だからできたのだという。
職人が一人、育つためには気が遠くなるような時間が必要だ。時間だけではない。材料費やその間の人件費もかかってくる。
それでも海外に出さないのは「目の届くところで凝った刺繡を手掛けたい」からに他ならない。もちろん、全く海外と取引がないのではない。海外へ出すのは先行商材があり、これと同じものをつくってほしいというケース。製品として形にしたことがあるので、糸や色、技法など最初に打ち合わせをし、1年後に検品と納品といったサイクルである。
基本は国内生産だ。したがって量産はできない。「量を追わないものをつくるのです」。顧客との細かい打ち合わせやスピーディな対応が可能なメリットを生かし、刺繡の図案の変更や悉皆も含めた刺繡による直し、刺繡糸の太さや技法の変更など、近くで作っているからこそできる。この機動力を生かしたビジネスを展開する。
デジタルとアナログを使い分け
熟練した職人の手が生み出す着物は究極のアナログの世界だ。染め、刺繡はもちろん、糸も含めて手業がものをいう世界だ。
だが、一方で最先端の技術を駆使して効率化を図っている。
たとえば、家紋。黒留袖や色無地に入れる家紋は顧客によって異なる。紋の見本を集めた紋帳に掲載されている一般的な家紋であれば、そこから選べばいいのだが、掲載されていないものも多い。こうした場合、オーダーを受けるときに顧客から写真や画像で家紋を渡される。これをイラストレータで取り込み、デジタルデータに変換する。こうすれば簡単に型紙を起こせる。手書きで家紋を起こすのに比べ、格段の速さである。
デザインを起こすときにもデジタル技術は活用されている。新規デザインをするのは当然アナログ。思い描いたものを手で表現する。しかし、一度図案が完成すれば、その後は手業ではない。その図案をデジタル処理して型紙を起こす。図案を残すのもデジタルである。
ここでポイントがある。出力は必ずモノクロで行う。カラーで出力すると、実際に着物での刺繡の色を選ぶときにそれに引きずられてしまうからだ。さらに、同じ図案を別の色合いでつくるときも原図に色がついていなければ、自由な発想で色を決められる。ITをツールとして使いこなしているのだ。

糸のマジックで布が生き返る
ファストファッションの対極にある着物。流通する期間は長い。5年、10年という歳月を経ても市場で価値を失わない。逆にいえばそれに耐えられる本物をつくりたいと村山氏は考えている。そして、その本物がつくれなければ、生き残れないのだ。
本物は流通期間が長いだけではない。世代も超える。「いい物だから、子供に」「孫に着せたい」。本物が持つ魅力がオーナーにそのような決断をさせるのだろう。
ところが、布は経年変化を避けて通れない。そのまま着用すると色褪せていたり、シミがあったり。そこで修復が必要になる。村山刺繡店でいま、依頼が多いのも修復だ。とくに黒留袖の修復依頼が増えている。

修復といえば、まず考えられるのが染め直しである。これは柄の部分を残し、地色を染めること。柄がそのまま残ることから、オリジナルに忠実に再生できる。
ところが、経年変化でできた孔や生地の傷みがあると、染めでは修復しきれない。そこで、箔や刺繡が登場する。孔の空いた部分に裏布を当てて補強、刺繡を施して修復、オリジナルを活かしつつも、よりよいものとするのである。
村山氏は修復と復元の違いを「見るだけか、実際に着用するか」と語る。見るだけであれば、布が弱くなっていてもなんとかなる。しかし、実際に着用する場合は力もかかるし、摩擦も起きる。それに耐えられるように仕上げるのが修復だ。
工房では黒留袖の修復が行われていたが、裏に布を当てて刺繡をする。新品であれば不要のこの裏布は弱った表地を支えるため。刺繡を施すことで布に強度を持たせるのである。時を経た黒留袖があでやかに再生する。

見違えるようになることは大きな生きがいだと村山氏は微笑む。着物は時を超えるロングライフ商品であり続けられるのは、新しく生命を吹き込む技があり、その技が連綿と伝えられているからに他ならない。
リスクを恐れずにチャンスを掴んでいきたい
着物人口は減少している。これは誰しもが認めるところだろう。そこにコロナである。コロナ禍が広がる中、村山刺繡店の受注も激減した。
ところが、村山刺繡店は強かった。その一つの要因が在庫である。受注産業をベースとする着物産業だが、在庫を持つことで、臨機応変、小売店や卸の急な変更やニーズにこたえられたのだ。また、悉皆を含めて幅広い業務をスピーディに対応できるのも大きな強みとなった。
とくに在庫については、受注だけのビジネスをしていたら、売り上げがゼロになりかねなかったと村山氏は振り返る。在庫があることで急なオーダーに応えて納品していくことができ、売り上げがたった。また、モノがあることで、顧客もイメージがしやすい。「こういう感じの訪問着で、もう少し華やかにしたいので柄を増やしてほしい」「ここを少し濃い色にして」といった具体的なオーダーができ、それが売り上げにつながっていったのだ。
そして、最大の強みが「仕事を選ばず、幅広いチャレンジをしたい」という志である。先代である父は「手が荒れる」と他の仕事を受けることを敬遠していたが、村山氏は着物に限らず、刺繡が生かせるもの、刺繡に関わるものすべてに取り組みたいという。たとえば、舞台衣装や幡などもそうだ。ある意味、割り切りも必要であり、販路が広がるのであれば、積極的なチャレンジもいとわない。

伝統工芸の集大成ともいえる着物。だが、逆に固定概念で常に考えているとその枠のなかから出られなくなるのも真実。思考回路も方策も、どうしても過去にとらわれ、固くなってしまう。ところが、違う仕事を手掛けていくと柔軟な考えや異なる視点を持つことができると村山氏。「自らが拓いていくんです」。
仕事は選ばず、品質に妥協せず。刺繡の可能性を広げていく。リスクはチャンスに変わり、日本刺繡が次世代に伝わる。