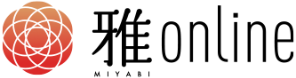匠探訪シリーズ3:染匠市川『高い技量に拘り、THE・市川を届けたい』
代表取締役社長 市川昌史氏

職人とお客様、今と未来をつなぐ架け橋
染匠(せんしょう)という職業がある。友禅染は江戸中期に宮崎友禅斎が京都で、扇面の絵画的模様を発展させ、着物に応用したことに遡る。
当初は各工房での仕事であったと推測されるが、次第に京手描き友禅染が産業として成立していく。産業として成立したころから、染匠という職業が確立されたといわれているが、これがいつのころかの定説は現在のところない。
では、染匠は具体的に何をするのだろうか。
これには現在の京友禅の工程の概略を知る必要がある。京友禅は着物のデザイン考案、つまり意匠考案に始まり、下絵、糊置き、引染め、挿友禅、刺繡、箔、紋入れなど、15以上の工程を経て完成される。各工程で専属の職人が己の技術を磨き、腕を発揮する。この分業制度が総合芸術である手描き京友禅を支えるといっても過言ではない。
分業制度であるから、各職人は独立した存在だ。創作する品にふさわしい技法や職人を選定し、携わる職人をまとめ、着物を作り上げる総合プロデューサーが染匠だ。客先と職人をつなぐ架け橋でもある。
染匠市川は創業74年。上品で美しい着物にこだわりを持つ染匠だ。

表情の柔らかさと遠近感にこだわり
美しい絵柄が描かれ、そこに金彩や銀彩の箔や粉、刺繡でさらにあでやかさを加えた京友禅。この着物が出来上がるまでには多くの人の手がかかっている。
友禅の工程は以下のようなものだ。
1 図案を元に、青花で反物に下絵を描く
2 下絵の線に従って糊置きをして防染(この後の色を挿す工程で色が混じらないように糊を置く工程)
3 挿し友禅(防染をした内側に色を挿して絵柄を描くこと)をする
4 伏せ糊(多色の友禅において、模様に色が入らないよう糊で柄を伏せること)をする
5 着物の色を染める(地染め)
6 蒸して色を定着させる(挿し友禅、地染めのあとに行う)
7 染料が定着したら生地に残った余分な染料を洗い流し(水元)、乾燥・湯のしをして、絹の柔らかな風合いを出し、加工でできたシワなどを取り除く。
8 金や銀の箔や粉などを施して華やかさを加え(金彩加工)、更に刺繡などを行い、最後に仕上げを施す。

それぞれの工程はエキスパートが担当するが、これを統括するのが染匠なのだ。染匠ごとに特色があるが、染匠市川の特長を一言でいえば、立体感と線の柔らかさだ。
同社が線の柔らかさを出すためにこだわっているのが糊置き工程である。糊置きは円錐形の筒に糊を入れて指先の感覚で糊を絞り出して線を描く。これが糊糸目であり、「金に糸目はつけない」の語源ともいわれる糸目である。
現在は扱いやすいゴム糊(化学のり)を使うところも多いが、市川ではもち米を主体にした糊(真糊)を使用する。調合は秘伝だが、絵の柔らかさやパッとみたときの印象が全く違うという。温度や湿度によって変化する糊糸目は手間がかかる。だが、この柔らかさこそ、京友禅の持ち味であり、市川の強みである。
この真糊はゴム糸目に比べて少し黄味をおびている。微妙な色調がやさしさとなり、優美な友禅染になるのだ。また、真糊は水洗いで落ちるため、ゴム糸目を落とすときのような揮発水洗工程が不要である。そのため、不必要に生地を傷めることがないメリットもある。
ただし、はっきりとした線が欲しいときにはゴム糸目を使う。使い分けをしていくことで幅広い表現ができる。
一方、遠近感や立体感を表現するのがぼかしである。これを行うのが挿し友禅の工程。糊糸目の内側に色を付けていく。色目や割合など染匠からおおよその指定はあるが、染料の調合や細部の色、ぼかしなど、個性とセンス、色彩感覚、さらに経験が問われる京友禅の“花形工程”でもある。
ここの段階で図柄に京友禅らしい柔らかさを出すと同時に、個々の図柄の立体感や着物全体としてみたときの奥行の深さなど、絵画的な表現を形にしていく。ちなみに業界で初めて濃い紫色の牡丹にぼかしをいれて表現をしたのが同社。それまでは牡丹の花は朱色や白で表現されることが多く、紫色を挿す表現は考えられなかったのだ。それがモダンで力強いことから評価され、ヒットした時期もある。

ところで、ぼかしは着物の図柄の表現でどこでも行っている手法。極端にいえば、インクジェットプリンタでもかなりの表現ができる。
では、同社ならではのぼかしはなにか。そこに感性がある。ぼかしは入れればいいというものでもなく、どこにでも入れればいいというものではない。手前の花や葉と遠景でぼかし方を変えることで、平面の反物のなかに、一幅の風景が現れる。風や花の香り、水の音も再現されていく。
一律にぼかしていてはここまでの表現ができない。センスが問われる上、バランスを考えて彩色する手間もかかる。だが、この手間こそ、真骨頂なのだ。

求められるコミュニケーション力とセンス、感性
“うちらしい友禅”と市川氏は表現するが、これを表現するのが職人だ。
“うちらしい”と染匠がオーダーしても、職人は別の人格。赤の他人である。好みも異なれば、「これがいい」と思う表現も違う。
そこで、職人さんとコミュニケーションを重ね、“頭の中で考えていることが一致するような関係”を築いていく。いわゆる阿吽の呼吸だ。これは一朝一夕にできるものではなく、少なくとも2~3年間は必要であり、長い年月をかけて育まれていく。だからこそ、“専属”の職人さんという表現に行きつく。
彼らが腕を発揮できる環境を整えるのも染匠の仕事の一つ。それがデザインであり、下絵である。同社では古今東西の美術作品集や写真集、過去の製品の原寸大のモノクロコピーなど、多くの資料を揃えている。
インスピレーションや着想を得るためのものだ。あくまでも発想の原点である。過去の作品がモノクロコピーであるのも、着色してあると、そのデザインを見たときに、色に影響されてしまうから。デザインを参考にしてもそこからさらに深めていきたい・・・という思いがのぞく。

揃えられた資料をどう生かすか、特定の作品のなかからどのようにモチーフの取捨選択をするのか。これには着物の知識や着姿を想定するイマジネーションとともにセンスが不可欠だ。さらに展示映えと着映えは異なる。展示では衣桁にかけて上前身頃だけでなく、下前身頃も見えるが、実際に着装すると下前見頃の図柄は隠れ、また背中の中心部には帯が重なる。この違いも考慮しなくてはならない。
もっとも、センスは即席で磨けるものではないというのも市川氏の持論。よい物はもちろんだが、悪いものも含めて多くのものを見て、感性を磨く必要がある。そして、それを経験値として蓄積し、習慣化していかなくてはならない。それにはある程度の時間が必要なのだ。

先代である市川氏の父は幼い市川氏にいいものを見る経験を積ませていた。「旅行にいくと常にその地域の一番の旅館やホテルに宿泊しました。『毎日、電気代とか節約しろと言っているのに、なんで、わざわざこんな高級な旅館に泊まるんだろう?』と幼心に思っていました。でも、そこに飾ってある絵や生け花、調度備品を見るとことに意味があったのです」。こうした体験が感性を磨く。長じて市川氏は「絵を見るのが好きになり、時間があれば美術館や博物館へあちこちに見に行った」。
幼少期からの経験の蓄積。市川氏に限らず、こうした京友禅や西陣の旦那衆の心意気が伝統を支えてきたのだろう。

「ザ・市川」をつくっていきたい
着物を取り巻く環境は厳しい。技術革新も進み、インクジェットプリンタの性能が向上、濃い色やぼかしの表現もできるようになってきた。インクの品質も高く、表面だけでなく反物の裏まで染まっている。
絵が描いてある点ではインクジェットも職人による手書きも同じだが、そこにかかる時間や手間は全くことなり、これが価格に反映される。こなれた価格が受け入れられやすいのも理解している。
だが、そことは一線を画す。ここで手掛けているのはオートクチュール。世界で唯一のデザイン(絵柄)が、長年にわたって磨いた技術によって作られていく。市川氏は「トップラインは崩さない」と覚悟を口にする。本当にいい物を知る人は少ないが存在する。「そこに向けてつくっていく」のである。

「オリジナルを見ていただきたい。その上でどこかで見かけて、あ、それ、市川の染めですね。知っている」といわれたいと市川氏。
ただし、好まれる色彩のトレンドも、顧客の好みも、着用する場も時代に応じて変化していく。それゆえ常に流行を意識し、多様な嗜好に対応できるようバリエーションも広げていく方針である。その意味ではフォーマルに拘らず、お茶席などで好まれる一般的なものも手掛けていくことになる。
他方、職人さんの高齢化も考慮、現在、世代交代の時期に当たることもあり、若い人材の育成にも注力する。
同社の工房では今春、京都の伝統工芸大学校を卒業して就職した女性が反物に挿し友禅をしていた。「自分でものをつくるということがどういうことか。作ったものがどう評価されるのかを身をもって知ってほしい」との考えから、デザインや色彩も含めて100%彼女のオリジナルだ。熟練の職人さんが色挿しをしている横で、彼女の真摯な瞳が筆先に向かう。

コロナの終息がみえないなか、着物を着て参加する会合やイベントは縮小され、業界でも大きな催事やイベントは開催できない。だが、技能が伝承されるよう、職人さんの仕事が途絶えないように。
「自社らしいものをつくる」―― 時代が動き、次のステージになったとき動けるように、いまできることをしていく。
「ザ・市川」へのこだわりが次世代への架け橋になる。