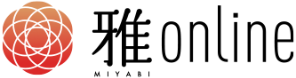『匠探訪シリーズ1:織楽浅野』引き立て合う 着物と帯 織を楽しみ、世界観を創造する

織楽浅野 代表取締役 浅野裕尚氏
着物通の間で「困ったときの織樂の帯」という合言葉がある。軽さ(結びやすさ、着心地)、おしゃれ感、上質感(光沢)を評価した言葉だが、もう一つ、重要な要素がある。
それは、コーディネートのしやすさだ。着物の醍醐味は柄と柄、色と色をコーディネートすることにある。その一方、着物と帯のコーディネートに悩むのも事実。それぞれが個性を主張し合えば、着物と帯は互いに引き立てあうのではなく、相殺してしまう。かといって、せっかく着物を着るのであれば、やはりちょっと凝ったもの、自分らしいセンスを見せたい。この矛盾を解決し、トータルで“決まった”と思えるコーディネートができるのが、織樂浅野の帯である。帯として主張しすぎず、没個性とならず、着物を引き立ててなお、きらりと光るセンスを加える。
意匠は東西を問わず古典から着想を得たもの、自然をアレンジしたものなど、幅広いが、いずれも浅野ならではのセンスが加味され、モダンにもクラッシックにも見えるもの。
しかも、織で細かな陰影や機微を表現するため、装う人の後ろ姿を味わいあるものに見せるのだ。

陰影のあや、そして素
織樂浅野のルーツは1924年にさかのぼる。現在の社長浅野裕尚氏の祖父政一氏がこの年に浅野織物を創業した。その後、1975年に父宏氏が株式会社浅野機屋を設立、そして1980年、裕尚氏が父宏氏とともに「織を楽しむ」をコンセプトに株式会社織樂浅野を設立、独立した。
裕尚氏の原点は23歳のときに他社が行っていた催事にある。この催事は呉服店でよく行われるもの。畳敷に帯が積み重ねられ、顧客は袋に入った帯をガサガサとさせながら、好みのものを探す。店舗スタッフは「いいものですよ。価値があります」「お似合いです」などと声をかける。これは使い捨て企画ではないか。さらに、帯の置き方にも強い違和感を覚えた。品質、手のかけ方、職人の手技、価格ともにエルメスやシャネルに匹敵するものを畳とはいえ直においている。これはもうブランドとは言えない。
使い捨てではない本当のブランドを確立しよう。
そう決心したときに出会ったのが谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』だ。『陰翳礼讃』は電灯がない時代の日本の美意識について論じたもの。薄暗い中でこそ育まれた感覚や美意識、生活と自然などが著されている。なかでも、ものの美しさは、ものそのものにあるのではなく、ものとものが互いに生み出すあやにあるという谷崎美学が裕尚氏の心を捉えて離さなかった。
着物と帯、互いのあやに美しさがあるはず。とすれば、引き立て合うためにはどのような帯がいいのか。両者がつくりだす陰影のあや。光と陰のなかにある無限の色彩と濃淡。その先にある精神的な豊かさや奥行き。何もないがすべてがある。これをどう表現していくか。
このとき、織樂浅野の独自性のベースができ、それを貫き通すこととなる。
文学だけではない。現代美術からもインスピレーションを得る。特に「表面は間である」をコンセプトとして版画を中心に油彩、ペーパーワークなど、多彩な活動を展開した井田照一との出会いは織樂浅野を語る上でなくてはならないものであろう。
あやは“もの”と“もの”の間にできるものだが、“もの”の本質はどこにあるのだろうか。それを裕尚氏は“素”と表現する。

これについて、裕尚氏は自社にあるレオナール・藤田のキャンパスを例に説く。藤田のキャンパスは乳白色である。ベースにシッカロールを使っていると推測されている。この工夫と手間が油彩のキャンパス地そのままでもなく、鮮やかな白でもなく、表面が平滑で透明感がありながらも優しげな雰囲気をつくる。ここにさらりと女性を描けば女性の肌になるのだ。下地、ベースの重要性である。
また、違う例では和紙が上がる。和紙は光線を吸収する。反射させ、まぶしいまでの白さを示す洋紙との違いだ。この柔らかさやしなやかさが魅力である。これもベースの重要さであるが、大切だからとことさら手をかけて塗りたてるのではない。かざりけ、いつわりのない本質がいい。それを一言で表したのが“素
”である。

帯でいえば、色や柄ではなく、ものづくりに向き合う姿勢、ニュアンスなどにこだわり、大切にしてきたのだ。
不易と普遍
時を超える生命を与えるのは情熱とエネルギー
織樂浅野の工房には幅広いジャンルの多数の資料、膨大な書籍、そして歴史的価値、民俗学的価値の高いコレクションがある。といっても漠然とした“コレクション”ではない。
しっかりと分類され、それぞれがストーリーを持ち、創造の源泉として活用されている。それはまた、「美とはなにか」「どのような作品が普遍性を持つか」「その帯は時代を超えて魅力を持ち続けるか」を問いかけてくる存在でもある。
たとえば、法隆寺伝来の蜀江錦。1300年前のものとは思えないほど、あでやかな赤が残る。経錦は3色の組み合わせをパターンとし、緯糸は主緯と陰緯の2丁で平織の組織として、経糸文様を表現したものだ。裕尚氏はこの裂について「美」は時空を超えるものと語る。


コレクションには龍村美術織物がジャガードで復刻したもの、さらに現代の模倣品も加えてある。現代のものは土産用として販売されている普及品だ。同じ色味、同じ模様を表現するが、深みや風合い、そこに流れる空気感が全く違う。
なぜか。それは1300年前の工人たちのそれまでにないものを創ろうとするチャレンジ精神、エネルギー、情熱がこの一片からほとばしっているのを感じるからであると指摘する。

法隆寺伝来の蜀江錦が織られた時は技法、柄、配色ともに流行の最先端。当時の社会ではかなりチャレンジャブルであったはずだ。だが、その“新しいものを創る”という情熱が時空を超えて、我々に語りかけてくる。それは逆に「新しいものを取り入れ、情熱を持ってつくっていかなければ取り残されていく」ことに他ならない。
また、筆のコレクションもある。動物の毛、鳥の羽毛など、“描く”という目的は同じであっても、ツールの種類は限りない。中に植物性の筆もある。1本の竹の先を細かくほぐしたもの。他方、わらを集めて束ねたもの。同じ用途であるにも関わらず、1つを分けていく方法と重ねていく方法である。両者の製作コンセプトは全く違う。モノをつくるというプロセスを振り返る教材でもある。

書籍やポスター、リボンの色見本、砥石、箸なども含め、自社で所有するコレクションは他社がまねできない。これが帯のアイデアの源泉であり、そのままアドバンテージとなる。40年の蓄積であり、集大成は織樂浅野の原点であり、未来への懸け橋だ。


この世界観を伝えていく
西陣の強みは分業システム。職人は特定の工程で自分の技を磨き、極めていく。織元は工程ごとに長年の付き合いがある職人に依頼し、一つの形としていく。職人の強みと強みをつなぐコンダクターとなるのが織元である。だからこそ織元は「何をしたいのか」「“らしさ”をどのように表現するか」を明確にし、伝えていかなくてはならない。
織樂浅野が得意とするのは、どちらかといえば洒落帯。自分の好みや意向で購入する層がコアな客層になる。そのため、現在は“らしさ”を認めてもらえるいい時代だという。これはリピーターが増えてきていることでも立証されている。リピーターが増えたことで「『前の帯とは雰囲気が違うけれど、こちらもいいわ』と言ってもらえなければならない」と気合も入る。少子高齢社会は進み、人口が減っている。着物を着る人となるとさらに減少している。が、それだけに分母を広げなくてはならない。そのためのツールはできるだけ多く持っておく方針だ。
独立から40年。洒落帯づくりに特化しているベースは変わらない。「この頃、デザインも丸くなってきた」と自らはいうが、その分、意匠は幅広いものとなってきている。最近では講演会を開催したり、和菓子店とコラボしたり。これまで築き上げたブランドとクオリティはそのままに、エンドユーザーに広く知ってもらう試みも進めている。

織樂浅野の魅力は帯そのものだけでなく、社屋、そこに置かれた家具調度、什器、雰囲気、室礼、帯のみせ方、あしらいなどにある。余白や余韻があるのだ。むしろ、こうした環境だから、やわらかで繊細、揺らぎのあるデザインが生まれたといえるのかもしれない。「この世界観を伝えたい」と裕尚氏。こうした空気感こそ陰影礼賛につながる部分かもしれない。
織元のコンセプトは織を楽しむ。消費者は帯で楽しむ。この帯に乗せて纏うのは穏やかで楚々とした“間”、そして、“素”に他ならない。