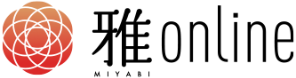『匠探訪シリーズ6:丸太遠藤』優美な絞りで独自の世界を展開
丸太遠藤 代表取締役 遠藤豊延氏

オリジナルにこだわり、技術を次世代につなぐ
日本、いや世界でも有数の花街・祗園町ご用達の老舗小売店に鍛えられた丸太遠藤。はんなり、華やか、かわいらしい絞りが特徴で舞妓さんたちの帯、長襦袢、帯揚げは同社の独擅場といってもいい。祇園を歩いていて、芸妓さん、舞妓さんが素敵な染め帯をしているなあと思ったら、まず、同社の携わったものだろう。遠藤氏も「納品で昼祗園に伺うとお稽古帰りの芸舞妓さんがしてはるのをよく見掛けます」という。
コンピュータ業界に在籍していた遠藤氏が、絞りの家業の世界に足を踏み入れて15年。職人を育て、オリジナルにこだわり、他社がやらないこと、きついことを手掛け、絞りの技術を継承、発展させている。
古(いにしえ)から愛された絞り
絞りの歴史は古い。インドや中国、中央アジア、さらにペルーなど、世界各地で発達している。布を絞り、あるいは折り畳み、染色すると美しい模様が表れる――技法はシンプルだが、古代の人々はそこに美を見出したのだ。現存するものは6世紀の中国の絹の絞りだ。日本では正倉院御物や法隆寺に伝わる裂が残されている。
正倉院や法隆寺などに伝わる裂に施された染めの技法は3種類。当時の名称でいえば絞り染めは纐纈(こうけち)。ろうけつ染めの臈纈、現在はほとんど行われていない板染めである夾纈(きょうけち)。この3つは三纈といわれているが、手の込んだ技は当時の人々の憧れの存在。大切に使われ、当時の人々の知恵の集積でいまに伝わる。
絞り染めが大きな発展をしたのが室町時代から安土桃山時代。さらに江戸時代に入ると絹を染める高級品の京鹿の子と有松に代表される綿に染める庶民派の絞りに分かれていく。

華やかな絞りは商人などの富裕層に大人気であった。だが、絞りは手でくくったり、器具で挟んだりと模様の一つひとつが工夫の連続で美を求めた手仕事。疋田絞りなどを全面に施すとなると、驚くほど時間と手間がかかる。当然、高価だ。そのため、江戸幕府の贅沢禁止令の対象となり、大奥でも禁止となったほどだ。
技術の灯を絶やさないために
長い間、愛されてきた絞りだが、現在、絞りを行う職人は減少している。丸太遠藤が抱える職人も高齢化が進む。技術継承ができるうちに何とか手を打たなければ、絞りの技術は消滅してしまう。
さて、どうするか。
跡を継いだ遠藤氏は長年放置され続けていた絞りの職人を育成しようと決意する。現在主流となっている中国などの海外で絞り加工を行うことは全く考えていなかった。「海外に出たら、戻ってこない」。国内産地での技術がそこで途絶えてしまうのだ。また、同社の顧客の細かいお誂えに対応する為にメーカーとしてサポートすることを意識する。日常遣いで着物を着用される方の納品までの期間は短く、臨機応変、言葉になっていない意思をくみ取り、形に仕上げていくにはやはり国内生産でなければ対応できないと考える。
そこで、まず、針と糸になじみがあり、布の扱いに慣れている全国の服飾関係の専門学校の協力を仰ぎ若い女性に声を掛けた。「絞り、やってみませんか。興味のある方、募集します」。このときに応募してきた女性を専属の職人として育成することにしたのである。
まず、一般的な絞りのテキストを配布、絞りの概要をつかんでもらった。次に京都へよび、仕事のやり方や流れをつかんでもらう。そのうえで、現役のベテラン絞り職人の元へ送り込む。技を学んでもらうためだ。
とはいえ、80歳の超ベテランの説明は長嶋監督流である。「スッとやって、サッとまとめればチャッとできる」。聞いている方は「????」。それでも基本的なことをテキストで学んでいたため、すぐにできなくても「こんなことだろうなあ」と想像できる。後は実際に手を動かして絞りの感覚をつかんだのだ。

その後も先輩から指導を受けてもらい、トライ&エラーを繰り返して修業、帯揚げ、風呂敷といった小さい物からスタートし、長襦袢、そして着物へとステップアップしていく。4、5年前から育成に取り組み始め、現在、数名が育っている。
「いま、育ちつつある段階というのが客観的な見方でしょう。けれども分業で工程が細分化されている着物の製造の世界では他の工程の育成も待ったなし。時間の余裕はないのです」。遠藤氏が考える熟練の域には達していないが、これから研鑽を重ね、さらに高みを目指していく。
そんな折、遠藤氏にとっても、若い職人にとってもうれしいことがあった。小売店から注文を受けて製作した着物で演歌歌手が紅白歌合戦に出場したのだ。「あ、私が絞った着物だ!」。モチベーションが上がったことはいうまでもない。
遠藤氏は「育てていくのは労力が必要。ただそれは必要な労力。」と言い切る。長野や大阪など各地に点在する彼女たちにまめにLINE連絡をする。それは「どうしている?」といった短いものであるが、個々に黙々と作業をする彼女たちが孤立しない配慮だ。
新人の発掘と育成と同時に中堅になった人にはブラッシュアップする機会を提供する。といっても、すでにそのレベルに達した人にコツややり方を教えてくれる職人は現在存在しない。どのようなやり方で絞ったのかが分からないものについては、遠藤氏と職人がディスカッションをし、現物を見てトライし、ゴールを目指す。
「続けていくからビジネス」と遠藤氏はいう。絞りという一つの道をひたむきに進む。携わる人すべてが継続していくことを強く意識しなければ途絶えてしまいかねない。すでに国産の絞り職人は絶滅の危機に瀕している。

もちろん、国産であればいいというものではない。「まず、そのものの纏う美しさや可愛らしさ、お客様からの素敵ですね、があって、それが国産だというのが理想」と遠藤氏。だが、一度滅んでしまった技術を復元することは難しく、復元できたとしても市場に受け入れられるかわからない。だから、灯を燃やし続け、一人ひとりに意義を問い続けているのだ。
着物に関わるすべての人を育てる
職人を育てるだけではない。着物産業に関連する人、携わる人を周囲が見守り、育てていくのが京都の着物関連産業の懐の深さでもある。
前述したように丸太遠藤も顧客に育てられたといってもいい。
チャレンジしたデザインが一般受けしそうになければ「いいわよ。私が着こなしてあげる」と気風のいいお姐さんが決めてくれる。大番頭がしっかりした小売店は、微妙な違いを指摘してくる。関わる人が企業の垣根を越えてが着物の文化を盛り上げ、携わる個々の店や職先、職人を育ててきた。この裾野の広さこそ伝統産業を支えてきたものであろう。
遠藤氏個人も街に育てられた一人だ。尾形光琳が居住していた社屋は祖父母の家。幼いころから正月などに集まっていたが、ビジネスを見ていたわけではない。家業を継ぐ決意で会社にきても「見て学べ」というスタンスの父。しかし、何を見て、何を学べばいいのかさえ分からない。当初2年間、「いつ辞めようか」とそればかり考えていたという。
それでも、いわゆる“おつかい”で得意先の京都市内の小売店を回り、いろいろなことを教えてもらった。小売りの仕立て部門にも出入りし、基本の寸法から学んだ。こうして2年が経過したころには着物の話をし、業界の水にすっかりなじんだのである。当時を振り返り、「七、八割は顧客から学んだ」と遠藤氏は振り返る。
新しい技術が新たな表現を生み出す
「継続は力なり」という。愚直に続けることで一つの技が磨かれていく。この“継続”は本人が継続したものだけでなく、技法や手法、創意工夫など、いってみれば過去からの資産すべてを含めた継続だ。時の積み重ね=継続が伝統という言葉で表されるのである。したがって、現在、携わっている人間は自分が歩んだ道だけでなく、過去から引き継いでいることを自覚しなければならないと気を引き締める。この自覚が顧客からの信頼につながり、世代を超えた信頼がいわゆる“かんばん”だ。
ただし、伝統は引き継げばいいというものではない。新しい技術も取り入れ、より洗練された形になっていく。

たとえば、絞りには桶を使用していた。染料を染め窯桶にいれ、そこに桶に挟んだ絞った布を入れ、染め上げるのだ。いまも桶絞りという技法がある。桶の木肌が得も言われぬ雰囲気を醸し出すが、白生地の反物を入れ、水を含んだ桶はとても重い。その桶を毎日のように動かし、持ち上げるのであるから染の職人は筋肉がつく。「筋肉隆々、マッチョな人しかいませんでした」。
ところが、現代では桶だけでなくビニール袋を使用する。絞り工程を終えた反物を絞りの部分だけ表に出し、ビニール袋で包む。このまま染めれば絞り部分だけに色がつく。ビニール袋と木樽。どちらが作業をしやすいかは明白だろう。肉体仕事であることは変わりないが、工夫の連続でかなり軽減されたことは確かだ。
さらに特筆すべきことがある。より表現が自由になったことである。ビニール袋であるから、任意の箇所に穴をあけることができる。その穴で模様を描くことができ、柄を自由にデザインできるようになったのだ。職人の日々の仕事の工夫から生まれる道具の進化が新技法へと昇華した。
また、同社では泥大島への織纐纈で染織特許を登録している。先代が濃い地色を染める技術を開発したのだ。泥大島をさらに絞り加工することなど、だれも考えなかった。だが、誰もやらないことをやる、常に前へ進んでいくと技術開発をしたのである。
そして、その思いは今日も続く。
「差別化がなければ前に進めない」。生地にもこだわり、丹後の機と取引し、精錬前の白生地を自社在庫として持つ。色も柄も雰囲気も、そして生地もオリジナルにこだわるからだ。徹底したオリジナルの追及は雑誌を見るのはご法度という方針にも表れている。見ればどうしてもその柄や色、雰囲気、感覚に影響されてしまうからだ。問屋や小売店からの問い合わせで雑誌掲載のものを指摘されると、「折り返します」と伝え、書店に見に行くというほど徹底している。

他社との違いこそが伸びる源。いや、それがなければ伸びない。時を超えた差別化の連続が技術を磨き、製品の完成度を上げていく。このプロセスが信頼となり、伝統になるのだ。