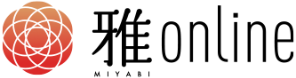『匠探訪シリーズ:2帯屋捨松』伝統とは地道に続けることそして新たな挑戦を
帯屋捨松 代表取締役社長 木村博之氏
1854年(安政元年)から西陣で工芸帯一筋に歩んできた織元・帯屋捨松。社屋は創業時期に建てられた築150年以上の町屋。
ここから織りだされる帯は確かな品質に裏付けされたフォーマルからさりげなくおしゃれな帯まで多彩だ。
老舗だけが持ちうる伝統と新しいものを積極的に取り入れる精神。さらに、それを自社のものとして昇華する技術。それらが相まってオリジナリティあふれる帯が生み出される。
“うち”にしかできないものを創る
その帯の製造から卸までの責任を担うのが織元だ。職先の確保や売り先との調整、さらに実際に結ぶ消費者の声を拾うこと。これらをトータルで行い、コーディネートしていくのが織元である。

その織元が一番はじめに手掛けるのがデザインだ。何をモチーフにするのか。どのようなニュアンスがいいのか、色彩はどうするのか—。そしてなによりも、帯として実際に締めた時の完成度である。
モチーフは多様だ。古代エジプトの壁画であったり、ビザンティン帝国のモザイク画であったり。

古今東西の名品を集めた画集が大きなアイデア源である。だが、これをコピーするのではない。そこに現代的な解釈し、自社流にアレンジを加え、帯として締めたときにどう見えるのかなどを考慮してデザインを決めていく。これには経験とセンスが求められるが、その部分こそ、織元の力量が試されるところでもある。
さらに、この着想を形にするときも一工夫ある。ニュアンスや陰影、カスレの表現を表すために画材は絵の具、クレパス、ペン、色鉛筆などを使用する。表したいもので変わるのだ。となれば、紋を起こすときも神経を使う。微妙な色遣いや感覚の違いを表すため「長年の付き合いのある、あ・うんの呼吸で意図を理解してくれる」職先に依頼し、製紋する。

織の段階でも自社で糸に複数の色をかけて染めあげ、理想とするデザインを実現するために必要な糸を作ることもある。

こうした一連の流れを「うちならではのプラスα」と称するが、そのプラスαこそ、帯屋捨松の強みである。同じようなモチーフや柄も、その時々の流行に応じて色遣いや空白のとり方が変わっていく。
時代に合致させ、常に磨いていく。製作は常に新しいものへのチャレンジなのだ。
10人のうち数人と相思相愛になりたい
いいものを作るポリシーがあっても、それは必ずしも世に受け入れられものでもない。
木村氏もじっくりとしたモノづくりができない時代になったという。
とはいえ、「相手が分からないから、この程度でいいだろう」とモノをつくり、経営をしていては、さらに地盤沈下してしまうと嘆く。だからこそ、つくり手が勉強すること、情報を発信していくことが必要だと指摘する。「(いいものをつくるのは当然だが)いいものをつくればいい」といっていると取り残されてしまうということだ。
しかし、工程や品質を一般の人が見分けることはかなり難しい。見た目に華やかで、見栄えのするものを安価に作ろうと思えばいくらでもできる。だが、パッと見のよさは飽きにつながる。
「浅いです。日本の文化は違うはずです」と木村氏はきっぱり。
「これまで、『今さえよければ』をやりすぎたのではないでしょうか」。つくり手とすれば、手を抜こうと思えばどこまでも抜ける。逆に手をかけようと思ったらどこまでも手をかけられる。
“今、売れるもの”“今、見栄えがいいもの”が果たして本当にいいものなのだろうか。
もっといえば、着物業界は、“手をかけた豊かさ”を提供できているのだろうか。木村氏は「現状に合わせていったら、沈むしかない。往々にして“売り”にいってしまうが、それでは安い商品へ流れてしまう」と現状を危惧する。自社の帯については「いいものしか作らない。10人いたら数人がいいと言ってくれるものを創っていく」と穏やかな口調の中に決意をのぞかせる。


確かな品質、おしゃれにして優美な雰囲気とセンスに加えて少量生産(同じものを着ている人がいない)というアドバンテージを持つからこその言葉の重みだ。
フォーマルは10人が10人とも“いいね“の帯でなければならない。逆にそうなるようにできている。だが、普段のちょっとしたおでかけに向くさりげなくおしゃれな帯は趣味性が高い。となれば、10人のうち数人が本当に好きになり、帯を眺め、身に付け、仕舞うという一連の時間や空間に、豊かさを提供することになろう。
木村氏は「この時代に着物を着るのであれば、もっと自由に楽しんでほしいし、着物の世界に憧れ、コーディネートや着方を見て、学んでほしい」と着る人にも訴える。「着付けが下手だからダメ」というのではない。フォーマルな世界は決まり事があるが、おしゃれの世界では自由な着方ができる。だからこそ、楽しんでほしいというのだ。
着物は決して安価なものではない。生活に必要なものでもない。それは着物が多くの人の手が必要とされるとても贅沢なものであり、非日常でもあるからだ。その豊かさをどうとらえるのか。
「縁側や床の間は一見、無駄なスペースです。しかし、そこに四季を感じるゆとりがあり、文化がある。これが世界観です」。たとえば、食器。極端にいえば、100円均一の商品だけで生活できるだろう。もっといえば、食器など使わず、紙皿であれば洗う手間さえ不要だ。だが、自分の好きな器を選ぶ人もいる。多少の値段の違いであれば、気に入ったもの、いいものを欲しいと思う人が存在するのだ。
どういう選択をするのかがライフスタイルである。「ごはん茶碗だけは作家物を使うというライフスタイルの若い方もいます。数は少ないですが、そういう方の存在があることで、こちらが全身全霊を傾けて、ものをつくり、その方たちに届けるチャンスがあると思えるのです」。
心豊かな生活をしたいという人たちに受け入れられている手応えはひしひしと感じているという。
愚直に真面目にやっていけば先は見える
同社の社屋は創業当時に創建された典型的な町屋である。
いい材料を使った空間はものの陰影が美しく映え、しっとりとした情感が漂う。ただ、不便さもあり、手がかかるのも事実。それでもいい材料を使って丁寧につくられた基礎や柱はしっかりとしており、次の世代に間違いなく引き継がれていく。建て替えは不要であることを考慮すれば、ロングスパンはリーズナブルでもある。コストパフォーマンスがよいのだ。
社屋だけではない。そこに長い年月の間に地道に積み重ねられた有形、無形の財産が帯屋捨松を支える。長年かかって作り上げてきたものがあるからできるわけであり、どんな優秀なデザイナーでも急にやれと言われてできるものではない。それが伝統だ。

例えば同社は莫大な糸を所有する。色ごとに分類され次の出番を待っているが、その在庫そのものが資産になる。イメージに合う色をこの中から選び出す。この時微妙な色合いを表現するための一色を作るために3色の異なる色糸をより合わせて1本にする。金糸、銀糸も同様にだ。
糸も欲しいものから手に入らなくなっていっている。危機感を募らせながら、将来必要になるであろうものから仕入していく。そう言った色彩に対する心意気が、西陣の捨松を作り上げてきたのだ。

ストックと同時に、情報の発信も怠らない。見てもらう機会を作り、帯屋捨松の存在をアピールする。帯だけでなく、着物のコーディネートを提案した展示会も行う。実際に帯を織っている工場での機織りのワークショップを行う。ブログやインスタを発信するなど多種多様な施策を使って捨松の帯の魅力をアピールしている。
いつの時代も憧れられる存在になる。まじめにやっていけば、まだまだいける。伝統を守るために挑戦をし続ける。木村社長は西陣織の未来に期待を寄せる。