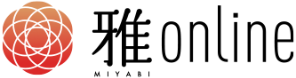吉野間道の美しさと深みとは?神聖さすら感じる錦霞染織工房を訪ねて

品川駅からバスで5分ほど。駅の喧騒から離れた静かな住宅街の一角に、藤山千春先生の工房、『錦霞染織工房』がある。
一見すると工房には見えず通り過ぎてしまうが、よく見るとガラス越しに機織り機が並んでいる様子が伺える。庭には木々が数本植えられていて、時折吹く風に葉の先が揺れていた。
入り口をくぐって中に入ると、数名の女性が染めの準備をしたり、機織り機の前に座ったりと活発な動きがある。おいそがしい最中ではあるが、藤山千春先生のインタビューまでの時間、機織りや染めの工程を見学させていただいた。
案内してくださったのは藤山優子さん。藤山千春先生の長女であり、ご自身も数々の名作を世に生み出す染織家だ。
未完成の吉野間道を目にする
優子さんに促されるまま、まず足を踏み入れたのは機織りが数台並ぶ工房だ。カタンカタンと乾いた音が小さな部屋に気持ちよく響く。
決して大きな音ではないが、まるで意志を持ったかのような、輪郭を感じる音だ。
2、3人の女性が集中した様子で、ほとんど何も言葉を発さずひたすら機を織っている。
機織りの音以外はほとんど物音がしない。時折ふと訪れる静寂に、どこか神聖さすら感じてしまう。
未完成の吉野間道を目にする貴重な機会。1mmにも満たない糸が何度も何度も往復することで、反物を形作っていく。
糸の往復だけを見れば精密機械の仕業かと見紛うが、そこには確かに熟練の職人の手が行う、丁寧で精緻な作業の繰り返しがあった。
2代目吉野太夫が由来の吉野間道
ここで吉野間道について簡単に触れておきたい。まず吉野間道の「吉野」は吉野太夫からきている。吉野太夫とは江戸時代、京の遊女の中でもトップクラスの地位に与えられた称号のことだ。
中でも2代目吉野太夫は、のちに語り継がれるほどの美貌と器量の良さを兼ね備え、身請けを希望した豪商から美しい織物が贈られたそうだ。
この織物こそ、今で言う吉野間道だ。それゆえ「吉野」の名が入っている。
さらに間道とは縞模様を指すが、縞模様に経糸(たていと)を交差させると格子柄になる。それゆえ、吉野間道の特徴は縞模様と格子柄にあると言える。
錦霞染織工房では糸の染色を草木染めで行なっているが、機械で作ろうとしても出せない微妙な色味や風合いの違いがある。これらの糸が縞や格子で織られた時、いっそう独自性が高く美しい模様となる。
織る工程を堪能していると、優子さんに声をかけていただいた。順番は前後するが、ラッキーなことに「染め」の工程も見学できるようだ。しかも、藍染めだ。
藍で染める。たかが一色、されど一色
地面に埋まった藍甕(あいがめ)の中をのぞく。藍というよりは、深く濃い黒に近い紫のような色の液体の水面が白く光っている。
けっして良い香りとはいえない、どこか鼻につく匂いが辺りにふわっと広がる。
甕には染料液(すくも)と呼ばれる液体が入っていて、この染料液の中に糸をつけていくのだ。
染める前の糸の束はご覧のように白い。糸の色が変わるのは染料液につけた時だけではなく、染料液から出して空気に触れた時により鮮やかに変わる。
黒に近い濃い青色の液体につけたのに、不思議なことに糸は鮮やかで艶やかな青に染まる。
液につける時間や空気に触れる時間、この工程を繰り返す回数によって色が変わるのだが、素人目には変数が多すぎてどんな色になるのか想像がつかない。
何度も何度も染めを経験することで培われる、言語化できない技術というものが存在する。
たかが一色、されど一色。青と一口に言えど、微妙な違いに目をやれば千差万別だ。気が遠くなる試行錯誤を経て、理想の青に近づけていく。
吉野間道の美しさと深み
最後に、吉野間道の着物をいくつかご覧に入れたい。これらは特別に見せていただいた着物たちだ。藤山千春先生が自ら、箪笥の奥から出して飾ってくださった。

素人目に見ても、吉野間道の美しさは際立っている。それは単純に言えば完成形として見た時のわかりやすい華やかさや彩り、模様の造形自体の美しさからくる。
ただ、それだけではない。最終的な美へと繋がる全ての工程において、細やかな技術と微に入り細を穿つこだわりがあるのだ。背景に思いを巡らせると、吉野間道はそれらが集積してできた純度が高い結晶のようにも見える。
今回、錦霞染織工房を訪れ作る工程を知ることで、吉野間道の外面的な美しさに加え、その「深み」にも触れられたのかもしれない。