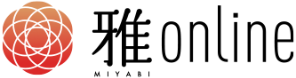結城紬の未来はいかに。新しい可能性を常に探す奥順の奥澤順之さんが思いを馳せること
結城市内を車が走る。そこかしこに蔵や時代を感じる商店が散見される。車通りがそう多くない静かな街並みを抜けると、不意に古き良き日本家屋の外観が目に入った。
ここは奥順株式会社が運営する結城紬ミュージアム『つむぎの館』だ。敷地内には資料館 反物の展示館、結城紬関連のショップや染織体験工房などが存在する。
私たちはここで、結城紬の着物を颯爽とまとった一人の男性と出会った。
静かな佇まいと柔和な雰囲気。凛とした佇まいながら、決して冷たさを感じさせない。初めてお目にかかる私たちにも気さくに話しかけてくださった。
この方が奥順の専務であり、次期社長にあたる奥澤順之(よりゆき)さんだ。
結城紬の伝統を受け継ぐという選択肢
順之さんは5代目の社長にあたる。伝統産業を受け継いで後世に伝える重圧は想像に難くないが、継がないという選択肢はなかったのだろうか。そもそも順之さんはどのようにして結城紬に出会い、どのようにして奥順を継ぐことを決意したのだろうか。
「私はいずれは奥順を継ぐことを考えていました。継ぐ、継がないの選択肢は頭になく、よほど何かがない限り、レールから外れることはないと考えていました。昔は自宅が隣にあって、会社と繋がっていたのです。ドアを開ければ会社だし、すぐそばに社員の方がいました。とにかく距離が近かったので、この産業の大変さも肌身で感じていました。」
順之さんは小さな頃からまさにここ、『つむぎの館』周辺で生まれ育った。周囲に職人さんが出入りする状況で、自然と結城紬にまつわる様々なものに慣れ親しんでいったのだ。
そんな環境で生まれ育った順之さんに、継ぐ以外の選択肢がなかったのも頷ける。順之さんは「自分だけここから逃げるわけにはいきませんよ。」と爽やかな笑顔とともにさらりと言ってのけた。しかし、すぐに家業を継ぐことはしなかった。
最初に就職したのは高級食器店のNAGAEだという。当時、六本木のミッドタウンにお店を構えていた。営業の一員として、飲食店やホテルに食器類を導入してもらうのが仕事だったそうだ。
NAGAEも陶磁器をはじめとした工芸品を扱ってきた会社だ。愛知県瀬戸市で地域に根差しつつ伝統を守り、革新的な試みを続けている。思えばどこか結城紬と通じるものがある。NAGAEの後は南青山の呉服店に1年、修行のために働いたのち奥順に帰ってきた。
結城紬との再会
ちょうど奥順に帰ってきたばかりのタイミングで、結城紬の素晴らしさに改めて気づく機会があった。
「私が奥順に入ってすぐ、プルミエール・ヴィジョンというパリの国際的な素材見本市がありました。フィリップ・パスケ会長という方にご招待いただいたのですが、造詣が深い事務局の方がパスケ会長に結城紬の話をしたら、わざわざ結城に足を運んでくださったのです。
パスケ会長は結城紬に感動して、『メゾン・ド・エクセプション』というプロジェクトを立ち上げました。日の目を見ていない素晴らしい技術に光を当てるというコンセプトで、結城紬をはじめ世界各地の作り手がブースに集まったのです。
私は当時、入ったばかりで何もわからなかったのですが、結城紬に人を感動させる力があると、改めて気づくきっかけとなりました。」
たとえいくつ国境を超えようとも、通底するのはものづくりにかける真剣な想いと情熱だ。結城紬には異国の地の人々ですら感動させる驚くべき力があった。
これは順之さんにとって、小さな頃から慣れ親しんだ結城紬の素晴らしさを、改めて別の角度から発見する経験となった。
これはまさに結城紬との再会だったと言えるのではないだろうか。
かつて生糸を返上した結城紬の職人たち
そんな結城紬に関する印象的な過去の話も聞いた。
かつて日本がGHQの占領下にあった時、ここ結城市も例外なく物がなかったため生糸が配給されたそうだ。当時の日本は列強に追いつき追い越せで需要は右肩上がり。その生糸を使って反物を作れば飛ぶように売れることは誰の目にも明らかだっだ。
それでも職人たちは真綿から糸を紡ぐことにこだわったという。反対する人もいたそうだが、結局は生糸をGHQに返上して、従来通りの作り方を貫いた。
「生糸で織るならもっと昔からそうしていたでしょう。物がないから生糸で織るというのは違うということです。」順之さんは遠くを見るような目でそう静かに語った。
自分が生まれる遥か昔から存在して、今なお連綿と続く伝統工芸。このようなエピソードひとつとっても、その重さを両肩にうっすらと感じるような錯覚に陥る。
先人たちから渡されたバトンを後世に伝えていく上で、順之さんは結城紬の未来にどのような思いを馳せているのだろうか。
見据えるは結城紬の未来
もちろん決まりきった答えなんてあるものではない。それでも真剣な表情で一点を見つめながら、「新しい可能性を常に探し続けることでしか、現状を打破できないのではないか。」と、順之さんは真摯な眼差しのまま答えた。
伝統工芸にありがちな話だが、伝統やしきたりを守ることが大事である一方で、それだけでは時代の変遷に飲み込まれてしまうだろう。奥順も革新的な試みを精力的に続けている。
「最近ではファッションブランドMINOTAURに、結城紬を使っていただいたパーカーやコートを作ってもらったり、ロールス・ロイスとコラボして結城紬の着物を着ながら試乗するといったイベントを開催したりしました。
このようなコラボやイベントを行うことで、着物を着る機会がない人にも届けられるように、情報の発信の仕方もいろいろと工夫しています。」
新しい試みを続けつつ、職人たちが余計なことを考えずにものづくりに打ち込める環境づくりに余念がない。これからの人生を懸けて何を成したいかとの問いに、一番に返ってきた答えがこれだ。
「職人さんが未来を描けるような環境づくりは今度もやっていきたいと考えています。この会社が続く限り。これは使命だと思うので。」さらにこう続ける。
「可能性を広げるという意味では、いろんな人に結城紬を見てもらいたいと思っています。いいんじゃない?でも、馬鹿らしいでもいいのですが、とにかく見てもらわないと反応がないので。中にはきっと何かつながる人がいるはずです。だから外にでて発信を続けていきたいです。」
「環境をつくる」も「発信を続ける」も一朝一夕にできることではない。まるで小さな波紋が重なり合ってゆっくりと大きな波をつくるように、毎日の積み重ねが折り重なって人を動かし、事を成していく。
それはまるで非効率でありながらも唯一無二を誇る結城紬の製作工程のように、時間をかけながらも着実に進展を見せる類のものなのかもしれない。
結城紬の未来について聞いて返ってきた順之さんの答えに、伝統を受け継ぎ後世に伝える人の確かな覚悟と、ひそかな楽しみが伝わってくるようだった。