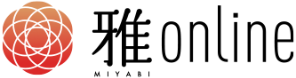偶然のデザインを楽しみながら。吉野間道の制作者、藤山千春
吉野間道をご存じだろうか。縞模様と格子柄が特徴的なこの織物は、着物をすこし学べば自然と耳に入ってくるほど広く知られた存在だ。
そして、この吉野間道の作り手といえば誰を思い浮かべるだろう。おそらく多くの人が口にする人物こそ、藤山千春その人である。
しかし、藤山千春さんにお聞きしたいのは、吉野間道についてだけではない。吉野間道との出会いを通じて、今までどのような景色を見てこられたかをお聞きしたいと思った。
準備が整い「先生、インタビューよろしいですか?」とお聞きすると、千春さんは静かな佇まいのまま小さく頷いた。気のせいだろうか、その瞳が微かに輝いたような気がした。
小さい頃から物を作るのが大好きだった
藤山千春のルーツをさかのぼると、幼少期のある思い出に行きあたる。
実は千春さんのお母様は八丈島のさらに南にある島、青ヶ島のご出身だ。ご両親の出会いも千春さんの生まれも東京だが、夏休みによく青ヶ島を訪れ、海水浴をして遊んだ思い出がある。
「八丈島に黄八丈っていう古くからある織物があってね。青ヶ島にも黄八丈の機織り屋さんがあったのよ。海岸に下りるまでの道に2軒ほどの機織り屋さん。その時はほとんど気に留めていなかったけどね。」
当時は何の気なしに通り過ぎていた機織り屋だが、今思えば確かに伝統工芸の存在が身近にあった。ただ”ものづくり”の道に進んだきっかけは、幼少期の思い出だけではない。ご本人の気質も大いにあったそうだ。
「小さい頃から手で物を作るのが大好きだったの。特に図工が好き。彫刻刀で一生懸命いろんな物を彫っていましたよ。そんな私を知る母の勧めもあって、女子美術大学に行って、工芸科で染色工芸を4年間勉強しました。」
染色工芸とは主に糸を染める工程のことだ。この時期に染織家としての原点が作られたことは疑う余地もないが、実は吉野間道との出会いは学生の時にはなかった。
藤山千春と吉野間道の出会い
千春さんは女子美術大学を卒業したあと、すぐに着物を作って売り出したわけではない。
「4年間ただ勉強したくらいで、すぐに売り物になるような立派なものは作れませんでした。卒業後は女子美術大学の先生でもある柳悦孝先生の工房が仙川にあったので、そこで2年間住み込みをすることにしたの。」
そう。吉野間道との出会いは、師である柳悦孝 氏との出会いを抜きには語れない。偶然とは不思議なもので、千春さんは吉野間道を学ぶために柳 氏に師事したわけではない。師事した先生が、たまたま吉野間道を作っていたのだ。
千春さんが住み込みをした2年の間、柳 氏は週3日ほど大学で教鞭を取っていた。そのため手取り足取り作り方を教えてもらったわけではなく、大学で習った基本的な技術をもとに、見よう見真似でなんとか師匠の技に近づけようとしたのだ。
そのような努力の積み上げで作った織物は、柳 氏の弟子が作ったということもあり、少しずつ少しずつ商品として売れるようになっていった。
たった一室で始めた教室
2年間の住み込みを経て、千春さんは柳 氏のもとを卒業する。品川の自宅に帰ると、一室で自ら着物を作りつつ教室を始めた。
「最初は一人で始めましたよ。一人の方が集中して作れます(笑)でもそのうち品川区、大田区に教室の看板を出したら人が集まるようになりました。最初に来た人は神戸の学校で勉強していて、基本的な技術はある方でした。今でも何人か教え子たちが残っていて、たびたび工房に着て着物を作っていますよ。」
千春さんは柳 氏に師事して吉野間道に出会い、幾年かののち今度は教える立場になった。たった一室から始まった教室はいつしか関わる人が増え、教室を増設して機織り機を増やし今の姿になった。・・・ここでふと疑問が生まれる。
デザインプロセスはまるでジャズセッション
先生と呼ばれる今でも染織家として現場に立ち、同時に作り手でもある藤山千春さん。千春さんが作る着物は、どれも複数の色彩が模様を織りなす、決して単純なデザインではない。
何もない無の状態から完成形に至るまで、千春さんは普段どんなことを考えながらデザインを起こすのだろうか。
「まず吉野間道の特徴は縞柄と格子柄ね。経縞、横縞、格子柄。縞柄がちょっと地厚に浮き上がって織られるっていうのが特徴。柄は複雑なんだけど、織る前に織ったときのことを考えて布を当てていくの。いろんな色を重ねて、隣の色との兼ね合いを見て、だんだんとイメージしていくのよ。」
千春さんはそう言いながら、実際に布を当ててデザインする様子を再現してくださる。目の前で繰り広げられる様子を目の当たりにして、ふと思ったことがある。
吉野間道のデザインのプロセス、これはまるでジャズセッションだ。ベースとなる布を感覚的に選び、その上に音を乗せるかのように複数の色を重ねていく。最初から完成が見えているわけではない。セッションを繰り返しながら、徐々に色合いを決めていくのだ。
当然だがパッチワークではないので、経糸の色と横糸の色が織り成って新たな色を作る。
たった一枚の布が糸の色や織り方(その幅や間隔など)といった、いくつもの複雑な要素が絡み合ってできていく。
もちろん計算もあるだろうが、デザインの様子を再現する千春さんは、どこか偶然をも楽しんでいるようだった。
さて吉野間道について、「最終的な美へと繋がる全ての工程において、細やかな技術と微に入り細を穿つこだわりがある。」と前の記事で書いた。しかし、いくら美しい作品であっても人の心を丸ごと動かすには何かが足りない。
数時間に及ぶ取材を終え、千春さんの話を反芻して気づいたことがある。
吉野間道について、いや、”ものづくり”について話す千春さんはどこか楽しそうなのだ。
もしかしたら作り手である千春さんの”楽しさ”があるからこそ、見た人の琴線に触れる何かがあるのかもしれない。あるいはその楽しさは、美しさ以上に人の心を動かすかもしれない。
いろんな色で染められたたくさんの布を、あーでもないこーでもないと重ねてはずらし、重ねては納得する千春さんの様子に、彫刻刀を手に時間を忘れて木を削るいつかの少女を確かに見た気がしてならないのだ。