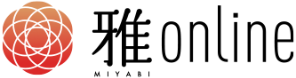【2025年 秋】首都圏のお月見イベント特集
中秋の名月・十五夜が、今年は10月6日にやってきます。日本の秋の風物詩として、古くから愛されてきたお月見。ここでは、首都圏で行われる風雅な「お月見イベント」をピックアップしてご紹介します。
今夏は暑すぎて、きものを着たくても着られなかった方も多いのではないでしょうか。涼やかに秋の夜長を楽しむお月見は、そんな方々にもピッタリです。久しぶりにきものを着て出かけてみてはいかがでしょう。
また、月見をさらに深く楽しんでいただけるよう、その由来や歴史などもあわせてお伝えします。よろしければご覧ください。
三溪園:観月会

三溪園は、明治時代に横浜の実業家・原三溪によって造られた日本庭園です。四季の草花に彩られる庭園に、京都や鎌倉などから集まった歴史的建造物等が巧みに配置され、古建築と自然が調和した姿を楽しむことができます。

ライトアップされた古建築を愛でながら庭園散策を楽しめるほか、「臨春閣」を舞台に日替わりで開催される「筝・尺八アンサンブル」「雅楽」「日本舞踊」「サックスとピアノ」「薩摩琵琶」の演奏もご鑑賞いただけます。
期間:
2025年10月3日(金)~10月7日(火)
時間:
9:00~21:00 ※最終入園20:30 ※観月会中のみ。通常は9:00~17:00。
入園料:
一般 900円 など
会場:
三溪園
住所:
〒231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷58-1
連絡先:
TEL 045-621-0634
公式サイト:
https://www.sankeien.or.jp
https://www.sankeien.or.jp/event/9308
向島百花園:月見の会

向島百花園は、江戸の町人文化が栄えた化政期(1804~30年)に、骨董商だった佐原鞠塢によって造られた庭園です。当時の一流文化人達による、庶民的かつ文人趣味豊かな庭として、大名庭園とも異なる美しさをもっています。

江戸時代から続く伝統行事で、篠笛や琴の演奏、お茶会、お供え式、絵行灯の灯りが庭園を彩ります。
期間:
2025年10月5日(日)~10月7日(火)
時間:
9:00~21:00 ※最終入園20:30
入園料:
一般 150円 など
会場:
向島百花園
住所:
〒131-0032 東京都墨田区東向島3-18-3
連絡先:
向島百花園サービスセンター 03-3611-8705
公式サイト:
https://www.tokyo-park.or.jp/park/mukojima-hyakkaen
https://www.tokyo-park.or.jp/park/mukojima-hyakkaen/news/2025/2025_10_5_10_7.html

また、向島百花園では9月13日~10月4日(「月見の会」前日)まで、「萩まつり」が開催されます。こちらでも秋の風情を感じてみるのはいかがでしょうか。
https://www.tokyo-park.or.jp/park/mukojima-hyakkaen/news/2025/2025_7.html
浜離宮恩賜庭園:浜離宮でお月見散歩 ~将軍の御庭で栗名月を愛でる~

浜離宮恩賜庭園は、将軍家の別邸ともなった江戸時代の代表的な大名庭園です。当時は「浜御殿」と呼ばれ、明治時代には皇室の「浜離宮」となりました。海水を導き潮の干満によって趣を変える「潮入の池」があり、都内で現在も実際に海水が出入りしているのは、この庭園のみになります。

11月2日にあたる「十三夜(栗名月)」にあわせて夜間開園し、伝統芸能の公演やガイドツアー、お抹茶や日本酒なども楽しめます。

期間:
2025年10月31日(金)~11月5日(水)
※10月6日の「中秋の名月」ではありませんので、ご注意ください(詳しくは後述)。
時間:
9:00~21:00 ※最終入園20:30
入園料:
一般 300円 など
会場:
浜離宮恩賜庭園
住所:
〒104-0046 東京都中央区浜離宮庭園1-1
連絡先:
TEL 03-3541-0200 (9:00~17:00)
公式サイト:
https://www.tokyo-park.or.jp/park/hama-rikyu
https://www.tokyo-park.or.jp/special/hamarikyu_moon-viewing
「お月見」の歴史
「中秋の名月」とは、旧暦(太陰太陽暦)8月15日の夜(=「十五夜」)に見える月のことで、この「旧暦8月15日」というのは、今年(2025年)は10月6日にあたります。また、詳しくは後述しますが、「十三夜」と呼ばれる旧暦9月13日の夜も月の美しい日として知られ、2025年は11月2日になります。
中秋の名月を観賞する習慣は、古くは唐の時代の中国に記録があり、平安時代頃には日本の貴族たちの間でも月見の宴が行われていたとされます。月を楽しみながら、楽器を奏でたり歌を詠んだりして、宴会を催すのが習わしだったよう。上でご紹介したイベントでも演奏や伝統芸能の公演があります。

その後、日本では旧暦8月15日の「十五夜」だけでなく、旧暦9月13日の「十三夜」や旧暦10月10日の「十日夜」など、年に何度も月見をしたそうです。例えば吉田兼好は『徒然草』の中で、(旧暦)八月十五日に九月十三日もあわせて、月を観賞するのにとても良い夜として述べています。
「八月十五日・九月十三日は、婁宿なり。この宿、清明なる故に、月を翫ぶに良夜とす。」吉田兼好『徒然草』第239段.

日本では農業の歳時と結びついて「十五夜」は「芋名月」、「十三夜」は「栗名月・豆名月」などとも呼ばれ、江戸時代には、月を見ながら豊作を願ったり、収穫に感謝したりするお祭りとして、広く民衆の間でも行われるようになりました。その際にススキを飾ったり、団子を供えたりする習慣も広まったようです。浜離宮恩賜庭園のイベントは「中秋の名月」の約1ヶ月後ですが、この「十三夜」・「栗名月」にちなんだ会となっていたわけですね。

おわりに
日本の人々は古くから、美しい月を愛してきました。折角のお月見ですから、古来連綿と受け継がれてきた素敵な感性を体感する機会にしてみるのも面白いのではないでしょうか。ということで、月を題材とした和歌を少しご紹介して終わりとしたいと思います。
秋風に たなびく雲の 絶え間より もれ出づる月の 影のさやけさ 左京大夫顕輔
秋風に吹かれ流れる雲の間から、もれ出てくる月の光の明るさ、清らかさを歌っています。
天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも 阿倍仲麻呂
遣唐使として唐に渡り官位に就くも、帰国の願いは叶わなかった阿部仲麻呂。どこであっても変わらない月の美しさから、故郷の山にのぼる月が思い出される情景を詠んだものです。地元から離れて暮らしている方は、そんな風に月を眺めてみるのもいいのではないでしょうか。
見る人に 物のあはれをしらすれば 月やこの世の 鏡なるらむ 崇徳院
「見る人に『もののあはれ』を知らせるので、月とはこの世の鏡なのだろう」。平安時代の文学によく登場する「しみじみと感じる情緒」。静かに月を眺め、心に生まれてくる感情を見つめれば、それがきっと「もののあはれ」なのでしょう。
参考文献
・OTSUKIMI「お月見とは。始まりと由来、歴史と地域のならわし」[https://otsukimi.jp/articles/kihon]
・―――「十五夜と十三夜 ~月を愛でる日本の風習~」[https://otsukimi.jp/articles/cMjU6QKt]
・―――「知られざる十日夜と三月見の魅力」[https://otsukimi.jp/articles/QqhzOXSS]
・国立天文台「中秋の名月(2025年10月)」[https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/10-topics01.html]
・奈良文化財研究所「三笠の山に出でし月かも」『なぶんけんブログ』[https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2009/08/20090801.html]